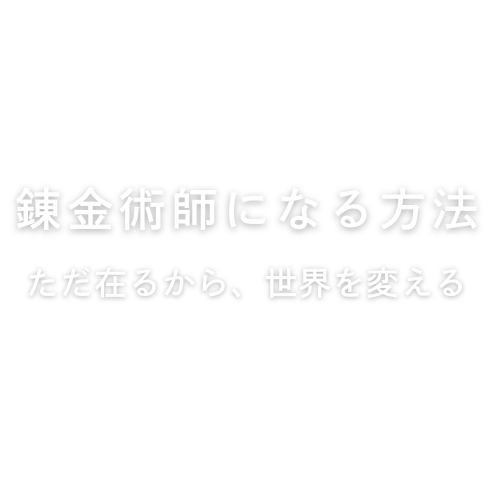Q:「仕事で最近モヤっとしてるのは何?」
A:「社長がベテランの人を無視してる。その日の指示とか、これからの報告も全部私に話してくる。8月から新しく入ってくる人、私につけて指導する。当然、ベテランの人は気分悪いし辞めるって言い始めてる。私も仕事しにくいし、間に挟まってるのがイヤ。確かに私は適当だけど、返事だけは良い。」
Q:「じゃあさ、なんで社長はAさんに振ってくると思う?」
A:「対応もいいし、仕事もそこそこ覚えてきたから。返事悪くしたら、ベテランさんと同じく無視される。仕事も任せてこないと思う。」
Q:「モヤッと何にしたと思う?」
A:「職場の雰囲気が悪くなってきてる。ベテランを差し置いて作業指導するからかな。後はベテランさんとの関係性。うまく仕事回せてたのにギクシャクしてくるはず。」
Q:「ベテランの人がいなくなったとき、自分の中で何が動揺すると思う?」
A:「いなくなったら、責任だ!この人に任せておけば大丈夫って思ってた。任されると認められるはほぼ一緒。私がいなかったら、当然ベテランさんに指示して指導も全部やってる。社長とベテランさんの両方の機嫌伺いながら仕事すると思う。」
Q:「もしAさんが今の職場で誰からも頼られなくなったとしても、それでも残りたいと思う?」
A:「残らない。」
Q:「頼られすぎても苦しい、頼られなさすぎても虚しい。Aさんにとって、ちょうどいい存在のされ方って、どんなふう?」
A:「頼られるのはそんなに嫌じゃないけど、自分より上の人がいるときは遠慮したい。たぶん、頼られるならもっと完璧に仕上げていたい。」
Q:「自分より上の人がいる状況で頼られるのは誰に対していや?」
A:「自分より上の人に対してイヤ。もっと完璧でもモヤっとはするけど、どっちかに指導してもらわないといけないならやる!」
Q:「嫌なのは、社長?べテラン?」
A:「ベテランさんに嫌だね。」
Q:「ベテランさんの何がいや?」
A:「自分を差し置いてって思われるのと、間違った指導したときに何か言われるかもしれない。」
A : 「思い出した。これって過去の記憶だ!」
Q:「過去の記憶を詳しく教えて」
A:「得意不得意の違いはあったけど、同レベルで仕事覚えてきた人がいた。Cさんにします。私の方が年下だけど、上司が昇格させようとして仕事の割り振りなど任されるようになった。そのときは私を含め4人で作業していた。当然Cさんにも指示するので面白くなかったはず。ウチらがやってきた仕事って、一から全部考えて作るので正解はない。私が指導していると、考えが違うCさんが『あんなやり方して〜』とか『あの教え方なに?』みたいなバカにする発言を聞こえるように言ってきた。それが何度もあった。」
●このやりとりから見えてくるのは、Aさんのモヤモヤの根底の存在定義は・・・
① 役割証明型
「仕事を任されている」=「認められている」
- 「私が返事がいいから」「対応しているから」社長は自分に任せてくる
- → 頼られることで「ここにいていい私」が成立している
→ つまり、頼られることでしか自分の存在を保証できない構造がある。
② 自己否定型
「間違ったことを言ったら、何か言われるかもしれない」
- 「差し置いてるって思われるのがイヤ」
- 過去にも同じような経験「実際に年上のCさんにバカにされた」→ 「私の指導や判断はいつでも否定されるかもしれない」という内なる自信の欠如
→ つまり、“やっていても、私なんかが言っていいのか”という無意識の否定感がある。
「頼られなければ不安。でも頼られすぎても怖い」
「やるのはいい。でも出すぎたと思われたくない」
「認められるのは嬉しい。でも否定されたら崩れる」
「完璧じゃない私が頼られすぎると危ない。だけど、頼られなければ、私はここにいられない。」
この定義がある限り、「ちょうどよく頼られるポジション」から降りることができません。
その“ちょうどよさ”を守ろうとすることで、逆に苦しさやモヤモヤを生んでいます。
◆ 「ちょうどよく頼られるポジション」とは?
Aさんにとっての「ちょうどよく頼られる」とは、次のような条件つきの安全地帯を意味します。
① 指導や判断の「最終責任者」ではないこと
- 自分より上の立場の人(=ベテランや上司)がいて、その人の“後ろ盾”がある
- その人が最終的に間違いを修正してくれる前提がある
- 自分は「中継地点」「手足としての実行係」にとどまっていられる
→ “責任は重くなく、でも戦力としては認められていたい” という微妙なライン
② 評価されるが、目立ちすぎないこと
- 「よくやってくれて助かってるね」と言われるくらいがちょうどいい
- でも、他の人から嫉妬されたり、「調子に乗ってる」と思われるほどでは困る
→ “目立たない範囲で有能とされること” を本人は無意識に選び取っている
③ 批判を避けられる位置にいること
- 自分の判断ややり方が公然と否定されるリスクが少ない範囲で活動したい
- 特に「ベテランに差し置かれてると思われたくない」「陰で何か言われるのが怖い」という過去の記憶から、“出すぎないように自分を抑える”傾向がある
◆ なぜこの「ちょうどよさ」にこだわるのか?
それは、存在定義が以下のように刷り込まれているからです。
- 「私は、完璧でなければ責められるかもしれない」(自己否定型)
- 「私は、役に立つことでだけ居場所がある」(役割証明型)
つまり100%頼られるのは怖い。でも、0%頼られないのは存在が消える
⇒ だから、その間の“60〜70%くらいの依存・信頼”が心地よい。
自分も「必要とされている実感」を得られて、かつ「責任が重すぎて叩かれる」リスクからも逃れられる。
「私は、信頼されすぎず、されなさすぎず、間違っても責められず、でも役には立っていると思われる場所にいれば、“存在していていい私”でいられる。」
でもこのポジションは、環境に大きく左右されます。外部依存的な居場所であり、
本人の定義が変わらなければ、いつまでも“自分の存在は他人の信頼加減で決まる”という構造から抜け出せません。
★錬金術師的な目線とは、現象を「ただの問題」として扱うのではなく、
それがどんな存在定義(無意識の脚本)によって創られているのかを見抜く視点です。
私たちは、自分でも気づかないまま「こうであるべき」「私はこういう存在だ」といった定義を抱えています。そしてその定義=周波数が、今の現実を創っています。
つまり、一見ネガティブに見える現象構成は、
その定義はもうあなたには不要ですよ、というサインなのです。
ここでは、その定義そのものをあぶり出して、構造を解体することが目的です。
再構築や書き換えは行いません。
定義の書き換えや、次の存在ステージへの錬成は、
ご希望の方にはセッションで個別にお手伝いしています。