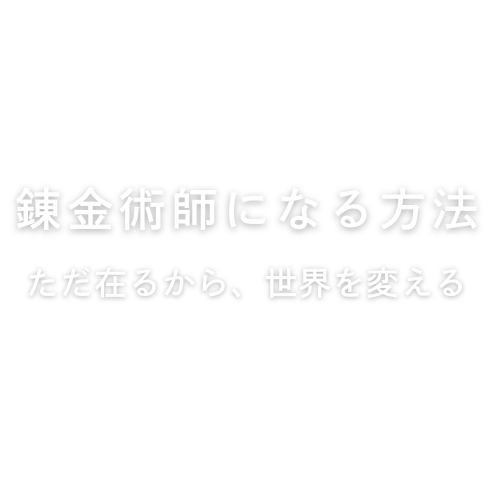最初に彼女が口にした悩みは、いかにも“正しい”ように聞こえました。ここからは、錬金術師の視点で問題としている現象を解体していきます。私は、いくつかの問いを通して彼女の内側を一緒に見ていきました。
Q:「そのままだとどうなって、自分にどうだからやめさせたいの?」
A:「食べ物けずって買ってるから良くないと思ってる」
Q:「本人が良いならいいのだけど、なぜそれを問題にしているのか?」
A:「買い物をやめる方がメンタルやられそうだから放置してる。気づくまで放置」
Q:「じゃあ、あなた自身はどうなの?」
A:「体調崩したら母を心配しないといけなくなり、自分に集中できなくなる」
Q:「お母さんがもう大丈夫になって、心配いらなくなったとき、何に向き合わないといけなくなると思う?」
A:「自分の人生」
Q:「自分の人生に集中したら、何が起きそう?」
A:「楽しいことが起きそう」
Q:「じゃあなぜ、ずっと人のことを考えてきたの?」
A:「親だからしょうがない」「めんどくさいけど、やってきた」
Q:「めんどくさいことをやり続けてきた理由って、なんだったと思う?」
A:「親だからしょうがない」
Q:「お母さんに小さい頃、一番言われた言葉って何?」
A:「何も言わなくても勉強してえらいね」
この「何も言わなくても勉強してえらいね」という言葉が、
彼女の存在定義だった。
裏を返せば、「言わずに気を利かせるあなたがいい子」「我慢して結果を出す子が正しい」という、沈黙と従順さを肯定する刷り込み。
それが、彼女の中に深く刻まれていた。
Q:「仕事辞めたとき、お母さんには言えなかったの?」
A:「お母さんには怒られそうだったから、生活が軌道に乗った段階で言った。お父さんには言えた」
Q:「お母さんって、どんな人に見えてた?好き?嫌い?」
A:「お母さんには感謝はしてるけど、好きという感じではない。お父さんは好き。おじいちゃんおばあちゃんは大好き」
そして、それが脚本の根になっているからこそ――
母の行動を“止めたい”本当の理由
彼女はずっと、母を「感謝はしているけど好きではない」と言いながらも、
どこかで“ちゃんとしていないといけない相手”として扱ってきました。
そして自分自身はというと、
「何も言わなくても勉強してえらいね」と言われて育ってきた。
つまり、感情を語ることも、欲しいものを欲しいと願うこともなく、
“期待に応える役割”を果たすことで存在を許されてきた子どもだったのです。
これは、私の分類で言う【第1層:役割証明型】の典型です。
「私は、役に立っているときだけ存在していていい」
「私は、ちゃんとしている限り愛される」
「私は、証明を続けることでしか、生きていてはいけない」
そんな彼女にとって、「母」が欲望のままに高額商品を買い続けている姿は、
ただの心配の対象ではありません。
むしろそれは、自分の存在定義を根底から揺るがすような、“許されている存在”に見えるのです。
私はちゃんとしてきた。
私は我慢してきた。
私は役を果たしてきた。
なのに、なぜあの人は――
「何も証明していないのに、存在している」
それが、許せなかったのです。
母を止めたいのではなく、
“証明なしに存在している人間”がそこにいることを、否定したかった。
なぜなら、それを認めてしまった瞬間に、
「じゃあ私は、なんのために“いい子”をやってきたのか?」と、自分の存在の根拠が崩れてしまうから。
この怒りは、実は怒りではなくて、羨望であり、諦めであり、
ずっと言えなかった
「私もそう在りたかった」
「私も許されたかった」
という、深い願いの痕跡なのです。
つまり彼女は、母を止めることで「世界の整合性」を保とうとしていた。
役割を果たしてきた人だけが存在していい世界を、守ろうとしていたのです。
もしそうでなければ、
今まで自分が握っていた“存在定義”が、まるごと崩れてしまうから。
この地点でようやく、彼女は問えるはずです。
「私は、何のために証明し続けていたのだろう?」
「私は、“証明しない私”を、まだ許していなかったのかもしれない」
さらに、私の定義する存在不安の6層に照らし合わせると、
彼女は第1層(役割証明型)と第5層(感覚喪失型)の複合タイプに該当します。
そして第5層は、感情や身体感覚を自分で感じることが難しくなるタイプ。
彼女は「めんどくさい」という言葉で多くの感情を抑圧し、
「楽しいことが起きそう」と言いつつも、どこかでそれに向かう力が湧かない状態でした。
このように、目の前の現象はただの“問題”ではなく、
存在定義そのものを問い直すために現れている“サイン”なのです。
自分はどのタイプなのか?
「私もこの相談者と似ているかもしれない」
「私はどの存在不安の層にいるのだろう?」
そう感じた方は、ぜひ書籍『リボーン ― ただ在ることに還る書』をご覧ください。
本の中では、6層の存在不安それぞれの特徴と、
その構造がどのように人生の現象として現れるかを詳しく解説しています。
ただ現実を変えるのではなく、
“なぜその現実が起きたのか”を、存在の定義から見直す。
そのプロセスに、きっとあなた自身の地図が見つかるはずです。
書籍のご案内
『リボーン ― ただ在ることに還る書』
この本では、6層の存在不安を含め、
存在定義・感情・身体・言葉・周波数のすべてを統合的に扱っています。
なぜ現実が変わらないのか
なぜ人の目が気になるのか
なぜ自分の感情が感じられないのか
その問いに、あなた自身が気付く本です。
まずは、今のあなたがどこにいるかを知ることから始めてください。
★錬金術師的な目線とは、現象を「ただの問題」として扱うのではなく、
それがどんな存在定義(無意識の脚本)によって創られているのかを見抜く視点です。
私たちは、自分でも気づかないまま「こうであるべき」「私はこういう存在だ」といった定義を抱えています。そしてその定義=周波数が、今の現実を創っています。
つまり、一見ネガティブに見える現象構成は、
その定義はもうあなたには不要ですよ、というサインなのです。
ここでは、その定義そのものをあぶり出して、構造を解体することが目的です。
再構築や書き換えは行いません。
定義の書き換えや、次の存在ステージへの錬成は、
ご希望の方にはセッションで個別にお手伝いしています。