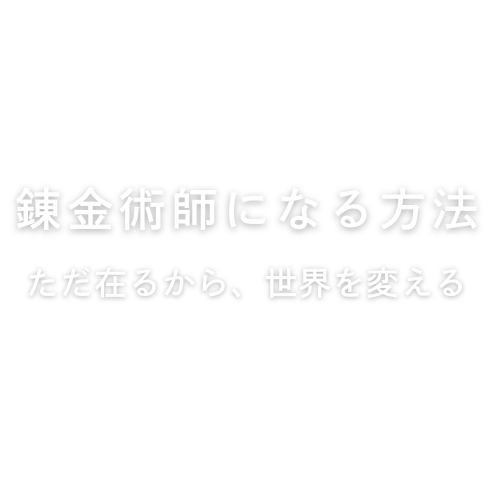誰にでも「私はこういう人間だ」という前提がある。
それは言葉にしていなくても、ずっと無意識に握ってきているもの。
たとえば
「ちゃんとしなきゃ」
「役に立たなきゃ」
「迷惑をかけてはいけない」
その裏には、「そうしないと存在できない」という定義がある。
つまり、“私はこうあるべき”という自分への定義が、あなたの存在の根っこにある。
それを存在定義と呼ぶ。
それは生まれた瞬間に誰かが決めたのではなく、
多くは幼い頃の体験や、家族・社会との関わりの中で自然と形づくられていく。
問題は、それが“自然”すぎて、自分が定義していることにすら気づかないこと。
そしてこの定義こそが、
あなたの人生すべてに、密かにそして深く影響を与えている。
たとえば──
✔「他人にどう思われるか」がやたら気になる
✔「役に立っていない」と感じると、居場所がなくなる
✔「うまくやらなきゃ」「認められなきゃ」という焦りが止まらない
✔「私が頑張らなきゃ」と常に責任を背負っている
✔「いいね」が欲しくてたまらない
これらはすべて、
自分の“存在”を 役割・成果・他者評価 によって定義している構造から来ている。
たとえば、自己肯定感が低いと感じる人も、
本当は「自己肯定感がない」のではなく、
「ある条件下でしか自分を肯定できない」という定義の枠組みに縛られていることが多い。
つまり、「存在定義」が歪んでいると、
どれだけ意識や行動を変えても、“根っこ”が書き換わらない限り、同じ現象を繰り返してしまう。
例えば、その存在定義とは、どんなタイプがあるのか?
● 役割証明型
→「役に立っていない私は存在してはいけない」
→ 常に“何かをすること”で存在を証明しようとする
● 多層喪失型(スケルトン)
→ 「感情・感覚・身体・自己認識・人間関係・世界との接続」など
多層的な不在感が折り重なって、空洞のような存在感覚になる
→ 何をやっても、どこか空虚で、本当の満足がこない
こうした存在定義は、
“自分を苦しめる”と同時に、“現実を決定する”ほどの力を持っている。
だから「なぜ頑張っても報われないのか」
「なぜ認められても満たされないのか」
「なぜ一人になると不安になるのか」
その答えは行動レベルの問題ではなく、
存在の定義そのものが歪んでいるからだ!
『リボーン ― ただ在ることに還る書』は、
その無意識に埋め込まれた存在定義に静かに光を当て、
“誰の反応も役割もいらない私”を思い出すための本。
あなたは、何もしなくても、
誰にも証明しなくても、
本当はただ「在る」だけでよかった。
その感覚を思い出したとき、
今まで“問題”だと思っていたものの根が、まったく違って見えてくるはず。
📗『リボーン ― ただ在ることに還る書』
もう証明しなくてもいい世界
▼Amazonページはこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHHK8NFK